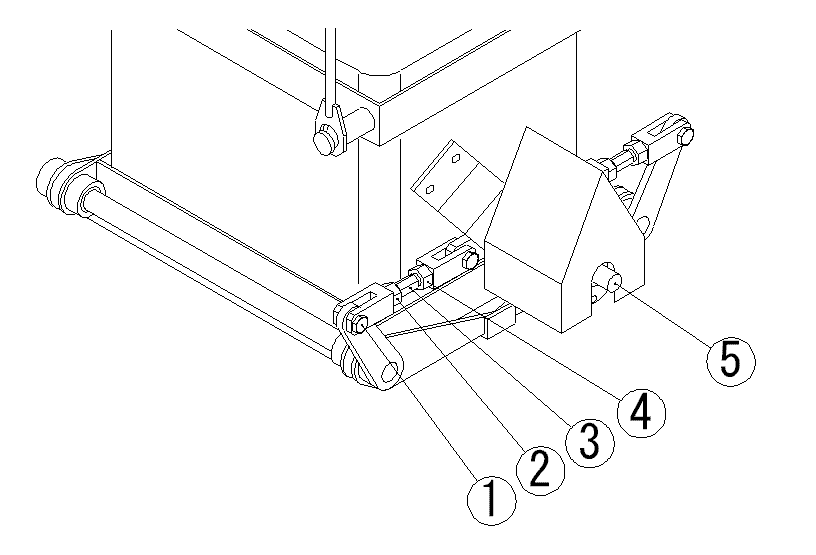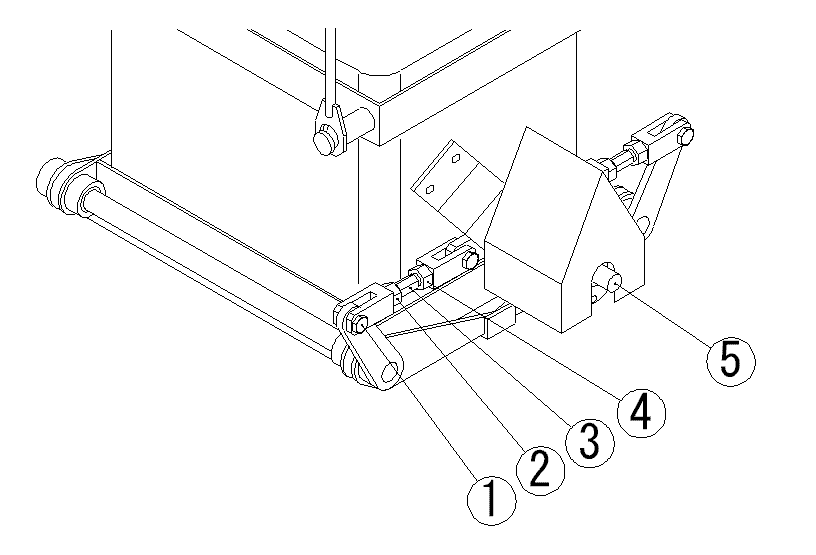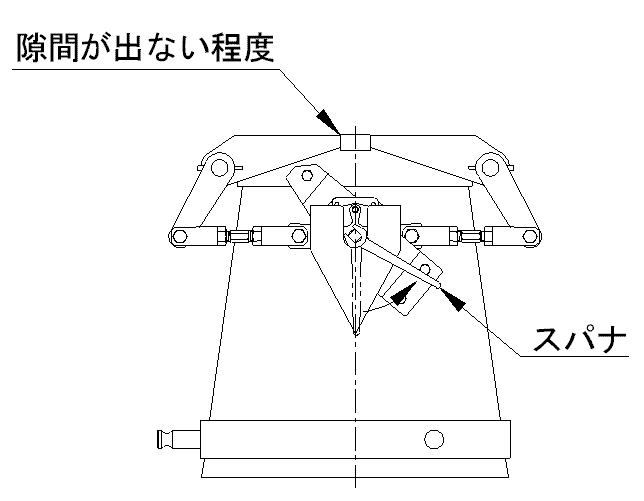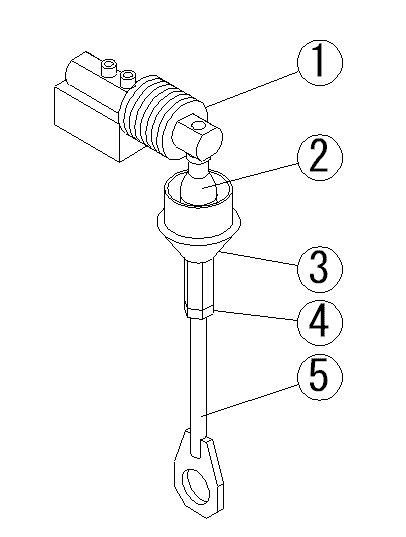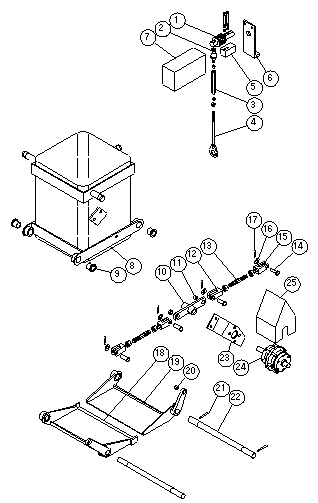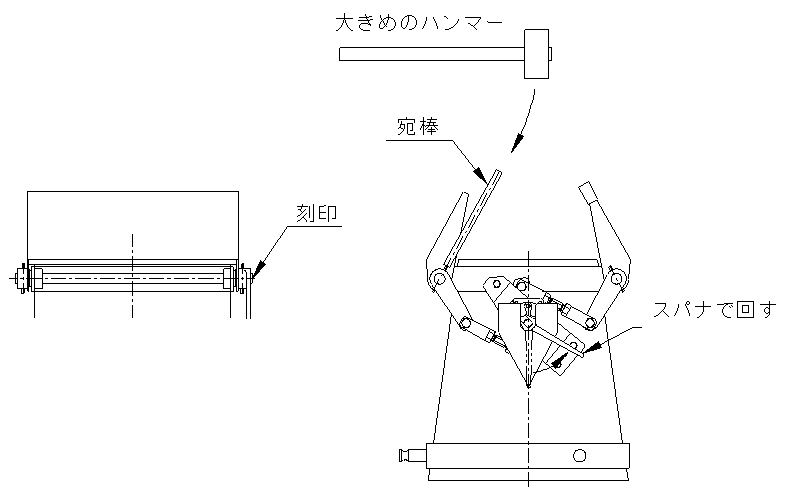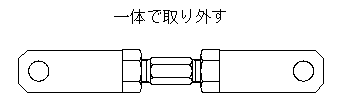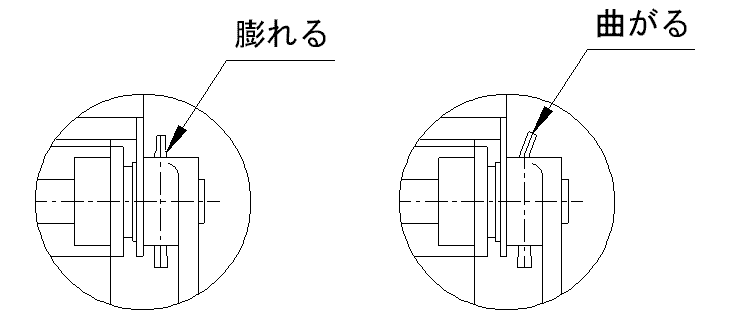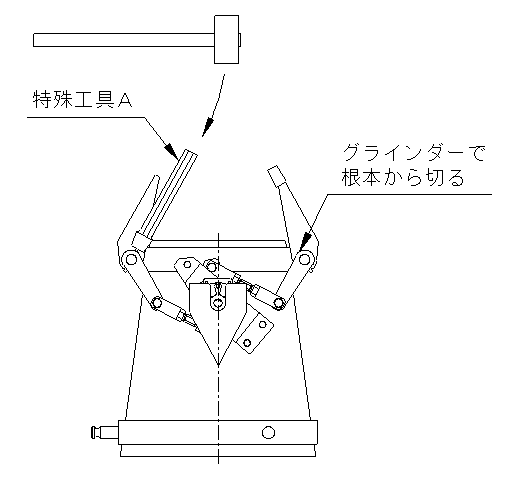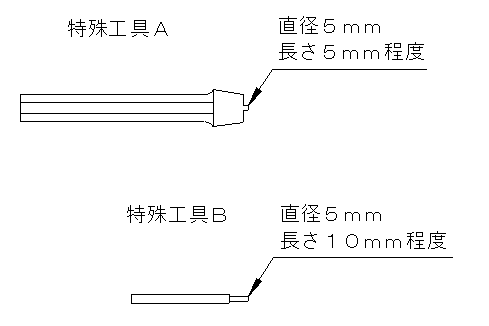定量槽(計量槽)
定量槽の下蓋は、閉じた状態で開閉腕が水平になり、左右の重量をお互いが持ち合う構造となっています。
この状態でエアーが途切れても(抜けても)中の製品は落ちません。
しかし、メンテナンスを怠りガタが発生すると、このような本来の能力を発揮できない場合がでてきます。
注意 定量槽を吊っているロッドに、多大な加重が掛かるような作業は絶対にしないで下さい。
重量を検出するロードセルが損傷することがあります。
付着性のある製品を計量する場合、下蓋の清掃はこまめに行って下さい。
下蓋の重なり部分の付着を放置すると、ブッシュの寿命が大幅に短くなります。また、隙間ができ(開閉腕が水平にならない)、製品漏れになることも考えられます。
下蓋の開閉スピード、開閉時間は適当か(計量物が完全に排出されているか)等の、動作を確認して下さい。
この作業は運転中行います。できれば終了間際、または作業開始時に行い、製品は抜き取って下さい。
清掃作業終了後、下蓋のガタや隙間、定量槽を吊っているロッド等の点検をして下さい。
注意 運転中の点検や動作確認はできる限り避けて下さい。
異物が混入したり、扉に付着している製品の落下で、計量誤差の原因になる場合があります。
調整作業は、できれば定量槽を本体から取り出して行って下さい。
また、調整の前には必ず点検・清掃を行って下さい。下蓋に付着物があると正しい調整ができません。
定量槽の下蓋は、下図②や④のロックナットの緩みにより、完全に閉じなくなる場合があります。
① ピン
このピンの軸受けにテフロンブッシュ
が使われています。(4カ所)
②④ ロックナット
右ねじ、左ねじとなっています。
③ 調整ボルト(ターンバックル)
このボルトで開閉機構の腕の長さを調整します。
⑤ ハイロータースパナかけ
この部分にスパナをかけ開閉テストを行います。
ロックナットが緩んで完全に下蓋が閉じていない場合、ハイローター(回転シリンダー)の開閉腕を水平にした状態で、③の調整ボルトを回して完全に閉じる長さに調整して下さい。
これが長すぎても短すぎても下蓋は完全に閉じません。
また、左右の閉まり具合が均等になるように調整して下さい。
左右の閉まり具合は、①のピンを回してみるとだいたいわかります。
開閉テストは、⑤の部分にスパナをかけて行います。
開閉スピードは、本体のシリンダー&電磁弁室の壁板に設けている、スピードコントローラにより、開閉時に異常音がしない程度に調整して下さい。
下蓋への付着もなく、ロックナットも緩んでいないのにガタがでている場合は、開閉機構の軸受けに使われているテフロンブッシュが損傷していると考えられます。そのような場合は早期にオーバーホールを行って下さい。そのまま放置しておくと軸受け部の穴が広がり、大修理になることもあります。
定量槽の重量信号を制御盤へ送るのがロードセルの役割です。この部品は計量器の命ともいえるものです。
ロードセルが正常な働きをするには、定量槽や吊りロッドに重量検出の妨げになるような外因があってはいけません。(例えば、計量室とロードセル取付部を隔離している防塵布が、粉塵と湿気により固まっている等)
定量槽点検時にはそのへんも注意して作業を行って下さい。
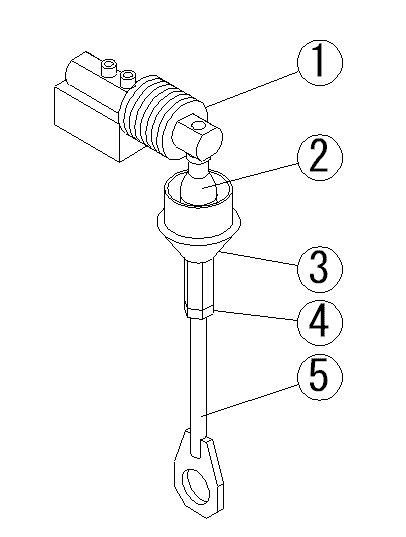 |
①ロードセル
重量を電気信号に変換する計量器の心臓部です。
②ロッドエンド
定量槽の揺れを吸収し、ロードセルを保護します。
③防塵布
計量室の粉塵を外部へ漏らさない為の部品。
④ロックナット
⑤吊りロッド
|
ロードセルの点検・調整には制御盤の操作が必要となります。もし、操作に不慣れな場合、別章「制御盤」の「ロードセル指示計」の項も併せてお読み下さい。
また、分銅検査には調整用分銅が必要となります。設定重量分の分銅を用意して下さい。
* 20kg計量器の場合、10kg分銅を2個用意する。
注意 用意した分銅は、検査用台秤(普段使用する台秤)にて検査する必要があります。
分銅重量が検査用台秤と合わない場合、正しいと思われる方を「正」として、
もう片方を同じ重量値になるよう調整して下さい。
ロードセルの点検は、分銅検査により行います。
正確な計量を行うために、分銅検査は定期的に行って下さい。
まず、定量槽へ分銅乗せ台を装着し風袋引きを行い、重量が「0」であることを確認します。
用意した分銅を分銅乗せ台に乗せ、乗せた分の重量が表示されるのを確認します。
注意 分銅は偏らないよう、左右(または前後)均等に乗せて下さい。
重量表示の確認は均等に乗せた状態で行って下さい。
偏った乗せかたでは正確な重量は表示しません。
「ロードセルの点検」で分銅重量と表示重量が合わない場合、ロードセル指示計の調整が必要です。
指示計の調整(較正)は、別章「制御盤」の「ロードセル指示計」の項を参照して下さい。
重量誤差が0~1目盛り(最小目盛りが10gの場合10g)程度の場合は、調整は不要と考えます。
誤差が1目盛り以上ある場合、定量槽を揺する等して、数回分銅検査を繰り返して下さい。
それでも誤差が解消されない場合、調整を行って下さい。
重量誤差が極端に大きい(Kg単位で誤差がある)場合、どこかの異常が考えられます。
最近袋詰めされた製品の重量検査を行い、問題なければ分銅検査のやり方に問題があるかもしれません。
もう一度機械周りを点検し、再度分銅検査を行って下さい。
それでも誤差が解消されない場合、また、袋詰めされた製品に不良品が見つかった場合、とりあえず指示計を調整し、正常に運転可能かの判断をして下さい。
正常な運転ができないと判断された場合、弊社まで連絡をお願いします。
ここに描かれている部品は標準機パーツリストです。
別添に「パーツリスト」がある場合、そちらを参照願います。
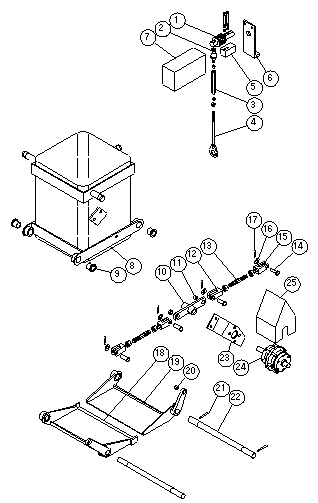
|
1.ロードセル
2.ロッドエンド
3.中間ナット
4.吊りロッド
5.ロードセル取り付け台
6.ロードセルカバー取り付け台
7.ロードセルカバー
8.定量槽本体
9.軸受けブッシュ(ARF-2225LD)
10.ハイローターレバー
11.軸受けブッシュ(AR-1210)
12.ナックルジョイント
13.ターンバックル
14.ピン
15.ナックルジョイント
16.ワッシャー
17.割ピン
18.下蓋(A)
19.下蓋(B)
20.軸受けブッシュ(AR-1210)
21.テーパーピン
22.下蓋軸
23.ハイローター取り付け台
24.ハイローター
25.ハイローターカバー
|
9、11、20番の各ブッシュ、及び14番のピンは1年毎の交換を奨めます。
上記交換作業を行う場合、17番の割ピン及び21番のテーパーピンは新品を使用して下さい。
ハイローターは5年毎程度で交換した方が良いでしょう。
定量槽(計量槽)分解方法
準備するもの
交換部品(ブッシュ、ピンなど)、ハンマー(3ポンド程度の物)、プラスチックハンマー、
潤滑スプレー、ウエス、宛棒(真鍮製φ16-200程度)
分解要領
定量槽を本体から取り出し、水平な床に逆さに(下蓋が上になるように)置きます。
床はなるべく頑丈で、傷がついてもいい場所を選んで下さい。
ハイローター主軸の反対側(外側)のスパナかけを使い、下蓋をいっぱいまで開きます。
21番のテーパーピンの径の細い方が上を向きますので、テーパーピンに宛棒を宛い、大きなハンマーで一気にたたいてテーパーピンを抜いて下さい。
下蓋がふらついて作業がやりにくい場合は、他の人が下蓋を押さえるとよいでしょう。
4本ともテーパーピンが抜けたら、22番の下蓋軸を抜いて下さい。
手で抜けない場合は柔らかい金属、または、木等を宛い叩き出して下さい。
堅い金属の宛物を使用する場合は、軸の中心だけに宛てるようにして下さい。軸端が変形してますます
抜けなくなる場合があります。
この軸は方向性があります。ハイローター側軸端に刻印があるので、確認して抜いて下さい。
次ぎに、ナックル部の割ピンを抜き、ピンも抜いて下さい。
ピンが錆などで抜けにくい場合、潤滑スプレーをかけ、ピンを回してやると抜けやすくなります。
両側ナックル、ロックナット、ターンバックル(調整ボルト)は分解しないで、上下左右がわかるように印をつけてから、一体で取り外します。
古いブッシュ類を抜き取り、清掃後組み立てます。
組立はブッシュ類を挿入後、下蓋軸から行います。
下蓋軸を刻印に合わせて挿入後、新品のテーパーピンを打ち込んで下さい。
テーパーピンはあまり強く打ち込まないで下さい。次ぎの分解時に抜けなくなります。
一体で取り外したナックル部を、方向に注意して組み込んで終わりです。
調整は、「調整」の項を参照して下さい。
テーパーピンの抜き方
定量槽のオーバーホールで一番難しいのが、テーパーピン抜きです。
このピンが抜ければ、作業の半分は終わったようなものです。
テーパーピン抜きのコツは、先ほども書いたように大きめのハンマーで一気にたたいて抜くことです。
しかし、肥料工場等の腐食性の製品を扱う工場では、それでもなかなか抜けないのが現状です。
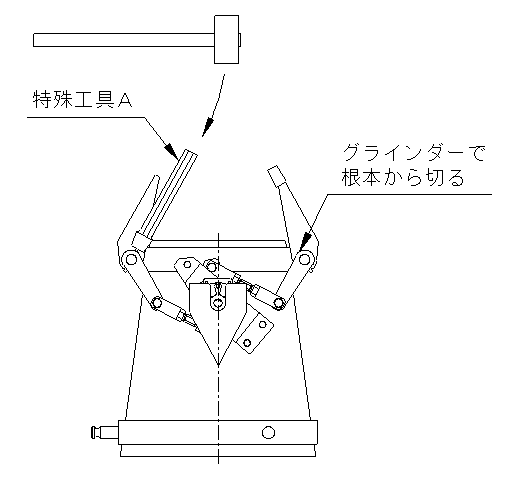
テーパーピンと宛棒が一直線になっていない場合、テーパーピンが曲がりますます抜けなくなります。
ハンマーの扱いが上手な人が叩いても、テーパーピンの根本が膨れて抜けなくなることもよくあります。
この様にテーパーピンが曲がったり膨らんだりした場合、特殊工具およびグラインダーが必要になります。
特殊工具は2種類用意します。
特殊工具A
1.タガネの先を、直径5mm長さ5mm程度に加工
したもの。(タガネ以外でも強度があれば可)
2.先端が直径5mm長さ10mm程度の強度のある棒
(リーマ、タガネなどで製作)
まず、曲がったり膨らんだりしたテーパーピンを、根本からグラインダーで切り落とします。
それから特殊工具A(図参照)をテーパーピンの中心に当て5mmほど打ち出し、残りを特殊工具Bで打ち出します。