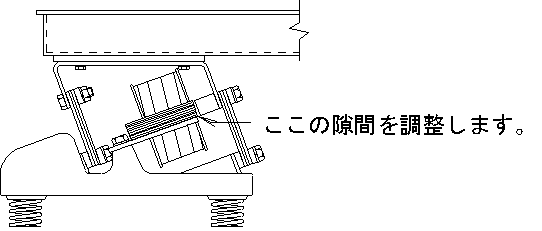表示灯・操作スイッチ
スイッチ類は常時使用します。また、取り扱いを誤ると怪我や故障につながります。
この章で取り扱いや機能を十分把握するようお願いします。
注意 表示灯が球切れになったら、早急に交換して下さい。
メンテナンス時、誤認などのトラブルにつながるため、大変危険です。
制御盤に電源が供給されていると点灯します。
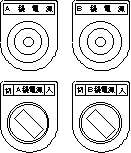
このスイッチ及び表示灯は、単能機の場合と2連筒以上で名称が変化します。
単能機の場合、制御電源スイッチと呼びますが、2連筒以上の場合、
「A機電源」「B機電源」「C..」「D..」と変化します。
表示灯も同様に、「A機電源」「B機電源」となります。
制御電源スイッチ「入」で制御電源表示灯が「点灯」します。
このスイッチは、出力機器の制御電源を「入」「切」します。
計量中には非常時を除き「切」にしないで下さい。
計量機の起動・停止は、始動スイッチで行って下さい。
銘板刻字
| 機械連数 | 単能機 | 2連筒 | 3連筒 | 4連筒 |
| 単能機 スイッチ | 切|制御電源|入 |
|
| 単能機 表示灯 | 制御電源 |
| 2~4連筒 スイッチ | 切|A機電源|入 | 切|B機電源|入 | 切|C機電源|入 | 切|D機電源|入 |
| 2~4連筒 表示灯 | A機電源 | B機電源 | C機電源 | D機電源 |
| 表示灯点灯時状態 | L11~L13間 ON | L21~L23間 ON | L31~L33間 ON | L41~L43間 ON |
片肺運転
部品等の故障で、いずれかの(例えばB機)計量機が稼働できない場合に、正常な方(A機)のみ
で計量機を稼働させたい時に、このスイッチを使用(B機を「切」、A機を「入」)します。
これで正常な計量機(A機のみ)の運転が可能となります。これを片肺運転と呼んでいます。
試運転
試運転時や被計量物の物性が異なるものを初めて計量する場合は、計量設定値(大投入・定量前・落差等)が適当な値かどうかまだわかりません。
このように、設定値が不安な場合には、前述の片肺運転と同様に制御電源スイッチを使用して、どれか一つだけ計量機を選択して、試計量します。
非常停止
標準の制御盤には、「非常停止スイッチ」は設けていません。
エアーシリンダー等は計量槽室内で駆動していますし、機械設置場所(通常、包装機の上部に設置)も、作業員の付近ではありませんので、緊急停止は不要と考えています。
「切|始動|入」スイッチは、1サイクル毎の起動・停止になります。
強いて言うならば、制御電源スイッチを「切」にすることで、計量中のものが即停止になります。
この場合は、計量槽に残っている重量を必ず手動強制排出して、再起動して下さい。途中からの継ぎ足し計量はできません。

計量機の起動・停止を行うスイッチです。
計量中に「切」にすると、1サイクル終了(排出終了)後、停止状態になります。
「入」(初回計量開始)時に、オートゼロが作動します。
停電等の主電源断時に「入」側のままであれば、シーケンサー内部では、計量機停止状態に 戻っています。電源が復旧しても、計量は始まりません。
電源復旧後、残量処理をし、「始動|入」の再操作(一旦「切」側にして、再度「入」側にする)が必要です。
重量異常時(過量・不足)のブザー警報時は、「切」でブザー停止になります。
停電保護
ME-C11タイプ(宮田ENG製)の制御盤スイッチの継承にて、起動・停止は切替スイッチ「切|始動|入」
にて製作してきましたが、停電によるトラブルが発生し、1993年(図番:NE150)から上記説明の停電保護 回路を付加しています。
押しボタンでの起動・停止
仕様書により、押しボタンスイッチでの起動・停止に変更している制御盤もあります。
大投入表示灯 : 大投入弁用電磁弁の状態を表示します。(点灯=ON)
中投入表示灯 : 中投入弁用電磁弁の状態を表示します。(点灯=ON)
小投入表示灯 : 小投入弁用電磁弁の状態を表示します。(点灯=ON)
制御盤最下段の、赤色の小さなランプに注目して下さい。
左から、大投入・中投入・小投入・排出の動作表示灯となっています。
①大・中・小 3ケのランプが点灯している時が大投入状態です。
② 中・小 2ケのランプが点灯している時が中投入状態です。
③ 小 ランプのみが、点灯している時が小投入状態です。
投入開始で大投入状態になります。
大投入完了で大投入状態→中投入状態に変わります。
中投入完了で中投入状態→小投入状態に変わります。
小投入完了で小投入状態→計量完了状態に変わります。
状態表示灯がない
この表示灯は、1990年後半に製造された、電気図番NE-0120以降の制御盤に設置されています。
それ以前に製造されていた、ME-C11タイプ(宮田ENG製)の制御盤パッカーユニットには、
大・中・小・完了・排出のLED表示がありました。
これと同等の状態表示灯があった方が使い勝手が良いということでNE-0120以降に、標準設置にしました。
従って、1988~1990年に製造された。F252使用の制御盤には、状態表示がない制御盤があります。

小投入動作をします。常時有効です。
現在では通常の包装作業では必要のないボタンになりました。
ロードセル式の初期の制御盤では、重量不足が出た場合は自動で補正投入しなかった
(手動にて補充するしか方法がなかった)ために、必ず必要としていました。
また、不足時の自動補充機能が付加された後も、ショック切れで計量完了状態になると、
かなりの重量を補充するために、強制小投入した方が早く処理ができます。
現在の制御盤では、ショック切れを起こしても計量完了にならずに、その重量値に対応する投入動作に戻ります。重量不足での補充投入量も、落差設定を極端に大きくする等故意にしない限り、以前より少なくなっています。
また、計量完了は、完了安定タイマーとMD信号(重量表示安定信号)を確認していますので、ショック切れで完了する事はないと考えています。
注意:MD信号を無視した場合は、ショック切れで完了する可能性が高くなります。
(MD信号は機能選択で無視できます。)
従って当社現在の制御盤では、小投入ボタンは操作する事がなくなったと考えています。
小投入ボタンがない
製作時には、ME-C11盤を継承のため、必ず小投入ボタンがあります。
しかし、このボタンに別の機能を割り付けて、違う機能を持たせるよう改造する場合があります。

計量完了(排出信号待ち状態)時に点灯します。
自動包装機に計量完了信号を出力します。
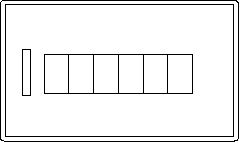
計量完了(強制完了も含む)した回数をカウントします。
計量過量の場合は、過量排出スイッチ「入」で処理すると、1回加算します。
これを、排出ボタンで強制排出処理すると、計数しません。

強制排出動作をします。常時有効です。
被計量物がなくなると、端量のまま計量中の状態が続きます。(計量完了にならない)
この端量を強制排出するボタンです。
排出動作については、「排出タイマー」の項を参照して下さい。
機能選択端子台を強制完了に選択していれば、強制完了ボタンとして動作します。
機能選択端子については、「盤内部品 機能選択端子台」の項を参照して下さい。
排出表示灯
排出表示灯 : 排出弁用電磁弁の状態を表示します。(点灯=ON)
警報を発します。警報の項を参照して下さい
PC(プログラマブルコントローラーの略)は、シーケンサーのことです。
サーマルトリップ時とシーケンサー異常時に点灯します。
詳細は警報の項を参照して下さい。
サーマルトリップ警報とシーケンサー異常表示を一つの表示灯で兼用しています。
パッカースケール本体にモーターが設置されていない制御盤は、銘板刻字がシーケンサー
異常になります。
不足・過量等の重量異常時に点灯します。詳細は警報の項を参照願います。

「過量排出|入」時:計量結果が過量であった場合でも、その計量を計量完了とします。
「切|過量排出」時:計量完了せずに計量機が一時停止状態になります。
警報は、過量排出スイッチの入・切に関係なく、過量なら出力されます。
従って、「入」時に過量になると、計量完了表示、重量異常表示、2つとも点灯します。
袋が装着されていれば、すぐに排出動作に移行しますので、警報はリセットされます。
過量排出「切」で使用したほうが良い場合
このスイッチを設ける以前は、不足以外の重量(正量および過量)は自動排出されていました。
被計量物が高価な場合や、客先でそのまま配合に使用する場合は、入れ目が多すぎてもいけません。
このような場合、過量を自動排出すると、過量製品がわからなくなるため、排出停止(一時停止状態) になった方が都合がいいようです。
過量排出「入」で使用したほうが良い場合
包装作業場を離れる場合、「切」にすると過量にて機械が停止します。
製造をストップさせたくない場合、「入」で使用します。
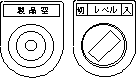
補助ホッパーの製品が下限レベル以下になると、製品空表示灯が点灯します。
この時、レベル切替スイッチが「入」であれば、その回の計量を完了し
排出後(1サイクルが終了後)停止します。(次の計量を開始しません)
製品が給ってくれば、自動的に計量開始します。
レベル切替スイッチが「切」の場合、補助ホッパーが完全に空になっても
計量を続けます。詳細は「レベル計回路」を参照して下さい。
盤内ステップダウントランスの2次側(AC100V)の電圧を表示します。
トランスタップ調整
ロードセル指示計の電源電圧は、AC100V±10%(F252)・AC100V+10%-15%(F800)以内となっており、 電源事情が悪い場合、電源電圧変動(電圧降下)により、ロードセル指示計がリセットされます。
セルフチェックを行っているF252等であればは、立ち上がりまで約30秒機能しなくなります。
以前に、前述同様のトラブルが発生したようで、それ以降電圧計を設置しています。
また、ステップダウントランス 220V,200V/110V,100Vのトランスタップ接続に誤りがある場合に、
容易にわかります。
A機小投入量調整・B機小投入量調整ツマミ
小投入電磁フィーダーの振動を強弱させるツマミです。
0(弱)→10(強)の銘板(図A参照)がついています。
振動の強弱を変えると、ロードセル指示計の落差設定の変更が必要になりますので
一度設定したら、変更しないようにしたほうが良いと思います。
(図A)
調整ボリュームだけでは、目的とする振動を得られない場合は、
電磁フィーダー本体の固定コアーと可動コアーとの隙間を調整します
別章「機械の保守」に詳細がありますので、そちらを参照して下さい。
(図B)
通常は弊社にて、隙間調整済みですので、
機械納入時は、弊社出張員の判断に従って下さい。
電磁フィーダー本体の固定コアーと可動コアーとの隙間の調整=粗調整
A機小投入量調整・B機小投入量調整ツマミの調整=微調整
と考えていただければ、いいかと思います。
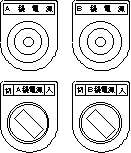 このスイッチ及び表示灯は、単能機の場合と2連筒以上で名称が変化します。
このスイッチ及び表示灯は、単能機の場合と2連筒以上で名称が変化します。
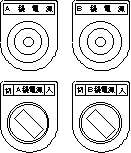 このスイッチ及び表示灯は、単能機の場合と2連筒以上で名称が変化します。
このスイッチ及び表示灯は、単能機の場合と2連筒以上で名称が変化します。
 計量機の起動・停止を行うスイッチです。
計量機の起動・停止を行うスイッチです。
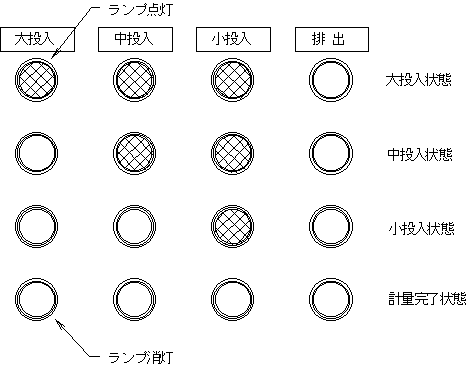
 小投入動作をします。常時有効です。
小投入動作をします。常時有効です。
 計量完了(排出信号待ち状態)時に点灯します。
計量完了(排出信号待ち状態)時に点灯します。
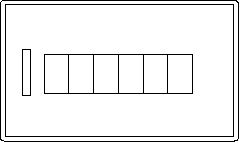 計量完了(強制完了も含む)した回数をカウントします。
計量完了(強制完了も含む)した回数をカウントします。
 強制排出動作をします。常時有効です。
強制排出動作をします。常時有効です。
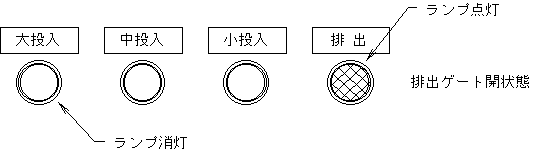


 「過量排出|入」時:計量結果が過量であった場合でも、その計量を計量完了とします。
「過量排出|入」時:計量結果が過量であった場合でも、その計量を計量完了とします。
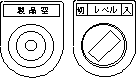 補助ホッパーの製品が下限レベル以下になると、製品空表示灯が点灯します。
補助ホッパーの製品が下限レベル以下になると、製品空表示灯が点灯します。